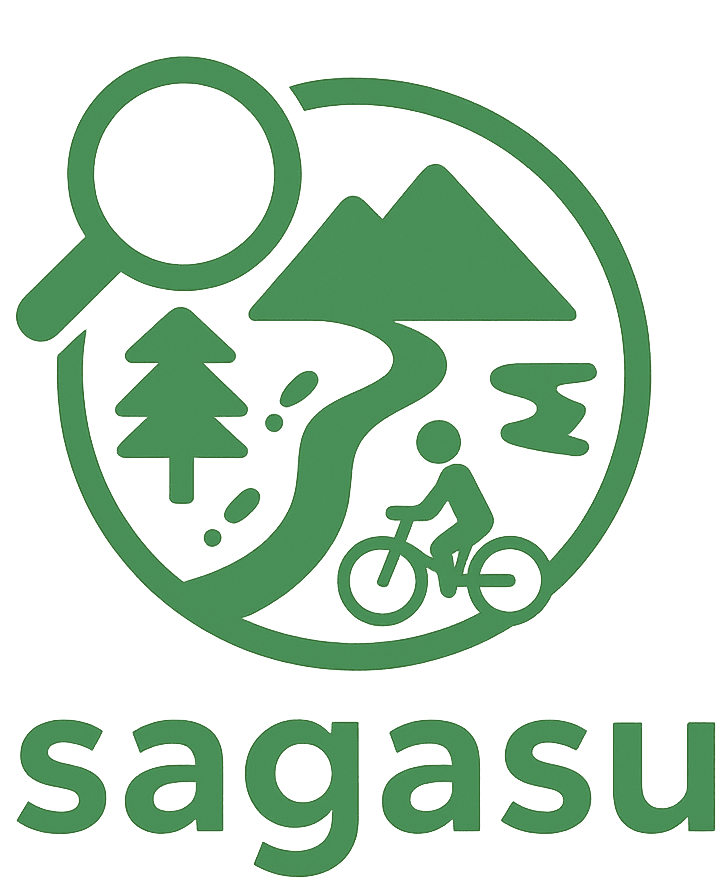冬の低山登山とは?夏山との決定的な違いとリスク

出典:YAMAP
「低山だから大丈夫」と考えていませんか? 実は冬の低山登山は、標高が低くても夏山とは全く異なる環境に直面します。標高1000m以下の低山でも、凍結や積雪により滑落や転倒のリスクが大幅に高まります。
筆者自身、初めて冬の高尾山(標高599m)に挑戦した際、装備不足で凍結した登山道で何度も転倒しそうになった経験があります。それ以来、低山でも冬季は専用装備を徹底するようになりました。
「低山=安全」ではない!冬山特有の3大リスク
冬の低山登山には、以下の3つの特有リスクがあります:
- 路面凍結(アイスバーン):日陰や北斜面では、気温が氷点下にならなくても路面が凍結します。特に早朝や夕方は要注意です。
- 低体温症(ハイポサーミア):汗をかいた後に風に吹かれると、体温が急激に奪われます。綿素材の服装は汗冷えを招き、低体温症のリスクを高めます。
- 日照時間の短さ:冬季は15:00〜16:00には日没を迎える地域が多く、行動時間が大幅に制限されます。下山が遅れると暗闇での歩行を強いられ、事故リスクが跳ね上がります。
※気象条件や山域により状況は大きく異なります。必ず最新の気象情報と登山道状況を確認してください。
なぜ専用装備が必要なのか?
夏山装備では冬の低山に対応できない理由は明確です。凍結路面での滑り止め(アイゼン)、汗冷えを防ぐ速乾性の高いベースレイヤー、防風・防水性能を持つアウターが不可欠です。
一般的な登山装備では、夏山は「濡れても乾けば良い」という考え方ですが、冬山は「濡れること自体が命に関わる」環境です。装備の選択基準が根本的に異なることを理解してください。
安全の要!「アイゼン(滑り止め)」の正しい選び方

出典:YAMA HACK
冬の低山登山で最も重要な装備がアイゼン(滑り止め)です。凍結した登山道や積雪路面では、アイゼンがなければ安全に歩行することはほぼ不可能です。
アイゼンには大きく分けて「チェーンスパイク」「軽アイゼン(4本爪・6本爪)」「本格アイゼン(10本爪・12本爪)」の3種類がありますが、標高1000m以下の低山であれば、チェーンスパイクか軽アイゼンで対応可能です。
チェーンスパイクと軽アイゼン(4本・6本爪)の違い
| 種類 | 爪の本数・形状 | 適した路面 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| チェーンスパイク | 11〜19本程度の小さな爪 | 平坦な雪道・凍結初期 | 軽量・コンパクト。足裏全体をカバー。深い雪では歩きにくい |
| 軽アイゼン(4本爪) | 土踏まず部分に4本の爪 | 緩やかな凍結路 | 最軽量だが安定性は劣る。お守り的な携帯向き |
| 軽アイゼン(6本爪) | 前後に各3本ずつ計6本 | 積雪・凍結のある低山 | 安定性が高い。4本爪より接地面が多い。つま先に爪がないため急斜面は不向き |
専門家の見解では、基本的には6本爪の軽アイゼンをおすすめします(oxtos公式ガイドライン、2025年10月時点)。4本爪は軽量でコンパクトですが、足裏の土踏まず部分しか爪がないため、安定性に欠けます。
【状況別】どれを選ぶべき?判断基準と推奨モデル
以下の基準で選択してください:
- 初めての冬低山・雪が少なめ:チェーンスパイク(モンベル チェーンスパイク、エバニュー U.L.チェーンクリートなど)
- 積雪5〜10cm程度・凍結箇所あり:6本爪軽アイゼン(モンベル スノースパイク6、エバニュー 6本爪アイゼンなど)
- 急斜面・本格的な積雪:10本爪以上のアイゼン(※本記事では低山向けのため割愛)
※路線や山域により規則や推奨装備は異なります。利用前に各山域の公式情報や登山道状況をご確認ください。
アイゼンと登山靴の相性チェックポイント
アイゼンを購入する際は、必ず自分の登山靴との相性を確認してください。特にチェーンスパイクやバンド式軽アイゼンは、靴のサイズや形状により装着できない場合があります。
- 靴のサイズ:アイゼンには対応サイズ(S・M・Lなど)があります。登山靴を履いた状態で試着することを強く推奨します。
- 靴底の形状:ソールが極端に薄い・柔らかいトレッキングシューズは、アイゼンが正しく固定できない場合があります。
- 固定方法:バンド式・ラチェット式・ワンタッチ式など複数のタイプがあります。登山靴のコバ(かかと部分の出っ張り)の有無により使用できるタイプが異なります。
※アイゼンバンドは経年劣化します。3年以上経過したものは交換を推奨します(エバニュー公式ガイドライン)。
徹底解説!冬の低山「服装・レイヤリング」の基本

出典:モンベル
冬の低山登山では、レイヤリング(重ね着)が体温管理と汗冷え防止の鍵を握ります。「たくさん着れば暖かい」という単純な発想ではなく、各層が異なる役割を果たすことを理解してください。
一般的な冬山レイヤリングは以下の3層構造です:
- ベースレイヤー(肌着):汗を素早く吸収・発散し、肌を乾いた状態に保つ
- ミドルレイヤー(中間着):保温性を確保しつつ、汗を外側へ逃がす
- アウターレイヤー(外着):風雨から身体を守り、内部の湿気を排出する
ベースレイヤー(肌着):汗冷えを防ぐ最重要アイテム

出典:山旅旅
ベースレイヤーは素肌に直接触れる最も重要なレイヤーです。冬山で最も危険な「汗冷え」を防ぐため、吸湿速乾性に優れた素材を選ぶことが絶対条件です。
主な素材は以下の2種類です:
| 素材 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 化繊(ポリエステル) | 速乾性が非常に高い。汗を素早く発散。リーズナブル。 | 匂いやすい。保温性はやや劣る。 |
| メリノウール | 保温性・調湿性が高い。防臭効果あり。肌触りが良い。 | 乾きが遅い。価格が高め。 |
一般的には、運動強度が高く汗をかきやすい方は化繊、保温性と快適性を重視する方はメリノウールが向いています。最近は両者の長所を組み合わせたハイブリッド素材も増えています(finetrack メリノスピンなど)。
※体質や発汗量により最適な素材は異なります。まずは1枚試して自分に合うタイプを見つけてください。
ミドルレイヤー(中間着):保温と通気のバランス
ミドルレイヤーは保温性を確保しつつ、ベースレイヤーから移動してきた汗を外側へ逃がす役割を担います。
代表的なミドルレイヤーは以下の通りです:
- フリース:通気性が高く、汗を素早く外に逃がす。行動中の着用に最適。薄手(100g/㎡前後)が低山向き。
- 化繊インサレーション:保温性が高く、濡れても保温力を維持。休憩時の防寒着として優秀(パタゴニア ナノパフ、アークテリクス アトム ジャケットなど)。
- ダウンジャケット:最高の保温性だが、濡れると保温力が激減。行動中ではなく休憩時専用。
低山登山では、行動中は薄手のフリースまたは長袖シャツ、休憩時は化繊インサレーションを追加という使い分けが一般的です。
アウターレイヤー(防風・防水):天候変化への備え
アウターレイヤーは風雨から身体を守り、内部の湿気を外に排出する役割を果たします。冬の低山でも天候が急変することは珍しくなく、防水透湿性素材(ゴアテックスなど)のレインウェアは必須です。
選び方のポイント:
- 防水性能:耐水圧20,000mm以上が理想(一般的なレインウェアは10,000〜20,000mm程度)
- 透湿性能:内部の蒸気を外に逃がす能力。数値が高いほど蒸れにくい
- フードの調整機能:風が強い日でも視界を確保できるよう、ドローコードで調整可能なものを選ぶ
やってはいけないNGな服装(綿素材など)
冬山で絶対に避けるべき素材が綿(コットン)です。綿は汗を吸収した後に乾きにくく、濡れたまま体温を奪い続けるため、低体温症のリスクが極めて高まります。
※綿素材の服装(ジーンズ、綿Tシャツ、スウェットなど)は冬山では絶対に使用しないでください。命に関わる危険があります。
その他の注意点:
- 厚着しすぎない:登山は運動強度が高いため、厚着しすぎると汗をかきすぎて逆に体温を奪われます。「少し寒いかな」程度が適正です。
- こまめに調整:登り始めは寒くても、10〜15分歩けば身体が温まります。汗をかく前に1枚脱ぐことを習慣にしてください。
【アイテム別】必須装備チェックリストと選び方のコツ

出典:YAMAP STORE
アイゼンと服装以外にも、冬の低山登山には多くの必須装備があります。以下のチェックリストで抜け漏れがないか確認してください。
①登山靴:冬用は必要? 3シーズン靴で対応できる?
冬の低山登山では、3シーズン用のトレッキングシューズでも対応可能です。ただし、以下の条件を満たしている必要があります:
- ソールが硬め:アイゼンを装着するため、ある程度の硬さが必要。柔らかすぎるとアイゼンが固定できません。
- 防水性がある:ゴアテックスなどの防水透湿素材を使用したモデルが理想。
- サイズに余裕:厚手の靴下を履くため、普段より0.5〜1cm大きめを選ぶのが基本です(※個人差があります)。
本格的な冬山(標高2000m以上、厳冬期)に挑戦する場合は、保温材入りの冬山専用登山靴が必要ですが、低山であれば3シーズン靴+厚手ウール靴下で十分対応できます。
②防寒小物:グローブ・ニット帽・ネックゲイター
手足や頭部は体温が奪われやすい部位です。以下の防寒小物は必ず携行してください:
- グローブ(手袋):薄手のインナーグローブ+防風オーバーグローブの2枚重ねが基本。行動中は薄手、休憩時は厚手を使い分けます。
- ニット帽:頭部からの放熱を防ぎます。耳まで覆えるタイプが理想。
- ネックゲイター(ネックウォーマー):首元の保温と防風。顔の下半分まで覆えるタイプは吹雪対策にも有効。
※手指の感覚がなくなると行動不能になります。必ず予備のグローブも携行してください。
③バックパックとその他(ピッケル・ストック)
日帰り低山登山であれば、20〜30L程度のバックパックで十分です。冬装備は嵩張るため、夏山より少し大きめを選ぶと良いでしょう。
その他の装備:
- トレッキングポール:凍結路面でのバランス維持に有効。積雪がある場合は長めに調整してください。
- ヘッドランプ(予備電池含む):日没が早いため必須。寒冷地ではバッテリーの消耗が早いため、予備電池を必ず携行してください。
- 地図・コンパス・GPS:積雪で登山道が不明瞭になることがあります。必ず紙の地図とコンパスも携行してください。
※ピッケルは急斜面や本格的な雪山で使用する道具です。低山(標高1000m以下、傾斜30度未満)では通常不要ですが、山域により判断が必要です。
④非常食・保温ボトル(サーモス)
冬山ではエネルギー消費が激しく、また低体温症予防のため温かい飲み物が非常に重要です。
- 保温ボトル(サーモス等):温かいお茶やスープを持参。身体を内側から温めます。容量は500〜750ml程度。
- 高カロリーの行動食:チョコレート、ナッツ、エネルギーバーなど。寒いと固まるため、ポケットに入れて体温で柔らかくしておきます。
- 非常食:万が一の下山遅延に備え、アルファ米やカロリーメイトなど日持ちする食品を携行。
※体力や行動時間により必要な食料・水分量は大きく異なります。初心者の方は多めに持参することを推奨します。
冬の低山登山で注意すべきポイント

出典:YAMAP STORE
装備を整えても、冬山特有のリスク管理を怠ると事故につながります。以下の注意点を必ず守ってください。
日照時間の短さと行動計画
冬季(12月〜2月)は日照時間が短く、関東近郊では15:30〜16:30頃には日没を迎えます。日没後の登山は視界が悪化し、転倒や道迷いのリスクが急増します。
行動計画の基本:
- 遅くとも15:00には下山完了を目標にする
- 登り3:下り2の時間配分で計画する(例:登り3時間なら下り2時間)
- 余裕を持った行動時間:冬は歩行速度が夏の7〜8割程度に落ちます
※例年の日照時間を参考にしていますが、山域や標高により異なります。事前に日の入り時刻を確認してください。
天候の急変と撤退の判断
冬山は天候が急変しやすく、晴天から一転して吹雪になることもあります。以下の状況では即座に撤退を検討してください:
- 風速10m/s以上:体感温度が大幅に低下し、低体温症のリスクが高まります
- 視界不良(ホワイトアウト):降雪や霧で視界が50m以下になった場合
- 疲労や体調不良:無理をすると判断力が低下し、事故につながります
※緊急時は無理せず下山・中止の判断を最優先してください。山は逃げません。また挑戦できます。
スマートフォンのバッテリー管理
寒冷地ではスマートフォンのバッテリー消耗が通常の2〜3倍速いという特性があります。GPS機能や緊急連絡手段として重要なスマートフォンを守るため、以下の対策を取ってください:
- 内ポケットで保温:ジャケットの内側ポケットに入れ、体温で温める
- モバイルバッテリー携行:容量10,000mAh以上のものを推奨。これも体温で温める
- 低電力モード設定:不要なアプリやBluetooth・Wi-Fiをオフにする
よくある質問(FAQ)
初めての冬低山、おすすめの山は?
初心者におすすめの冬低山は、高尾山(東京都・標高599m)、筑波山(茨城県・標高877m)、大山(神奈川県・標高1,252m)などです。登山道が整備され、万が一の際もエスケープルート(下山路)が複数あるため安心です。
ただし、これらの山でも冬季は凍結や積雪があり、専用装備が必須です。必ずアイゼンと防寒装備を持参してください。また、初めての冬山は経験者と同行することを強く推奨します。
アイゼンはいつ装着すればいいですか?
アイゼンは凍結や積雪が確認できたら即座に装着してください。「もう少し先まで大丈夫」と判断を先延ばしにすると、滑って転倒するリスクが高まります。
一般的な装着タイミング:
- 登山道に雪が積もっている(深さ3cm以上)
- 路面が凍結している(キラキラ光る・滑りやすい)
- 日陰や北斜面に入る直前
装着は安全な平坦地で行い、装着後は爪の状態を必ず確認してください。緩んでいると歩行中に外れる危険があります。
装備をレンタルできる場所はありますか?
はい、やまどうぐレンタル屋やそらのしたなどのオンラインレンタルサービスで、アイゼンやウェア、登山靴などを借りることができます。料金は1泊2日でアイゼン1,000〜2,000円程度、登山靴2,000〜3,000円程度が目安です(2025年10月時点)。
また、登山口近くの登山用品店(高尾山口の石井スポーツなど)でもレンタルを行っている場合があります。ただし在庫状況により借りられないこともあるため、事前予約を強く推奨します。
※料金や在庫状況は変更される可能性があります。利用前に各サービスの公式サイトでご確認ください。
まとめ:冬の低山登山は「正しい装備」が安全の絶対条件
冬の低山登山は、夏山とは全く異なる世界です。「低山だから大丈夫」という油断が、命に関わる事故につながります。本記事で解説したアイゼン(滑り止め)、レイヤリング(重ね着)、防寒小物は、どれも安全登山の必須条件です。
筆者自身、初めての冬山で装備不足を痛感し、それ以来「装備は命を守る保険」と考えるようになりました。最初は費用がかかりますが、レンタルを活用しながら少しずつ揃えていくことをおすすめします。
正しい装備と知識があれば、冬の低山登山は夏山とは違う静寂と美しさを堪能できる素晴らしい体験になります。ぜひ安全第一で、冬山の魅力を楽しんでください。
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。装備の規格や推奨基準は変更される可能性があります。登山前に必ず最新の気象情報・登山道状況を確認し、自己責任のもと慎重に判断してください。